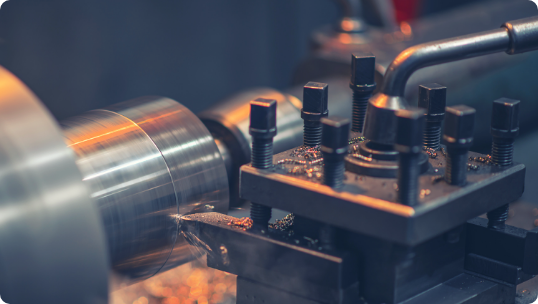ましんつ~るまがじん~vol.36~
INDEX
・今日のコラム………… 見本市特別委員会とは(第1回)
・統計更新情報………… 2012年1月次受注短観発表
・編集後記 ………… 輸出管理講習会を終えて
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇ 今日のコラム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○見本市特別委員会とは(第1回)
今号からは、見本市特別委員会についてご紹介します。
見本市特別委員会は「日本国際工作機械見本市(JIMTOF)の諸対策等
の実施、及びこれに関連する調査研究」を所管しています。
2011-12年度は、樫藤達郎委員長((株)カシフジ・取締役社長)の
もと、79社81名の委員で構成されています。
委員は、各社で営業技術や販売促進に携わる方々が比較的多数ですが、営業
マンや総務、技術系の方も多く、他の委員会に比べて職種が多様であることが
特徴と言えます。
見本市(展示会)は自社の知名度向上を図る機会であると同時に、多くの受
注を獲得するビジネスの機会でもあり、また、各社の製品が一堂に集うことか
ら、技術力を目に見える形で競う場でもあります。どの視点から見本市を捉え
るかは各社様々であり、これが委員の多様な顔ぶれとなって現れています。
今回はまず、日工会とJIMTOFの関わりについてご説明したいと思いま
す。
JIMTOFは大阪国際見本市・東京国際見本市という、戦後の産業復興、
市場拡大を目的とした「総合(産業)見本市」から1962年(昭和37年)
に分離・独立して発足しました。
現在では、日工会と(株)東京ビッグサイトが共催でJIMTOFを開催し
ていますが、日工会はJIMTOF全体の展示面積の約半数を占める最大の出
展団体でもあります。
JIMTOFの円滑な運営に向けて日工会内の意見を集約・調整することが、
見本市特別委員会の最大の役割と言えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 統計更新情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○2012年1月次受注短観発表(2012年1月31日15時公表)
短観(2012年1月次)
1、業況に関する判断(DI)
(a)会社全体の業況 足元 4.5 翌月 6.0
(b)工作機械事業の業況 足元 4.5 翌月 7.5
2、工作機械受注の先行き予測に関する判断(DI)
(c)受注総額の水準 足元 1.5 翌月 3.0
(d)受注内需の水準 足元 -3.0 翌月 -1.5
(e)受注外需の水準 足元 3.1 翌月 4.6
3、受注内需業種別の水準(DI)
(f)一般機械向けの受注水準 翌月 1.5
(g)自動車向けの受注水準 翌月 1.6
(h)電気・精密向けの受注水準 翌月 -6.1
4、受注外需地域別の水準(DI)
(i)アジア向けの受注水準 翌月 4.6
(j)欧州向けの受注水準 翌月 -7.4
(k)北米向けの受注水準 翌月 3.4
(ひとこと)
1月次の受注短観では、足元の受注総額、内外需とも減少しました。翌月は
全てやや持ち直しているものの、内需業種別や外需地域別のDIは全て減少し
ており、国内外の設備投資環境にやや慎重な見方が広がりつつあるのではない
かと思われます。
■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
○輸出管理講習会を終えて
当会が開催する「工作機械の輸出管理講習会」が終わりました。
今年は全国5会場で計6回開催し、約380名の方々が参加されました。
輸出管理に関する政省令・通達の中身や、その運用は複雑で理解が難しいとの
声も囁かれる中で、当会としてもどのように解り易い内容にしていくかが今後
の課題です。
特に、若い社員や営業、サービス、設計・開発部門などの方にも簡単に理解を
頂けるようなものを別途企画できるよう、裏方として努めていきたいと考えて
おります。
(H)
次回、Vol.37は2012年2月9日(木)に配信予定です。
毎度最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
次号もよろしくお願いします。
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
【ましんつ~るまがじん】
■ご意見ご感想はこちらまで
send@jmtba.or.jp